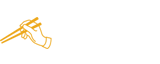築地新館
築地でお気軽江戸前寿司
2016年「ふじつぼ」を入荷しました
2016/5/16
ふじつぼは、味がカニミソのようだということで、珍味として人気を集めるようになっています。
一見すると食べられるものではないように思えるのですが、青森県などでは多く食べられてきた食材です。
ただ、大量に捕獲されるようになってきたことで量が激減してしまい、高級料亭などで食べられる高級食材となっています。ふじつぼは独特の甘みを持っていて、口に入れるととろける舌触りを楽しむことができるのが特徴です。
岩場でよく見られるふじつぼは、軟体動物の一種だと考えられていましたが、特に注目を集める存在ではありませんでした。しかし、研究が進められてきた結果、軟体動物ではなく甲殻類の一種だということが分かってきました。
また、注目されているのは味の良さだけではなく、磯の風味を感じることができる点も魅力となっています。
数ミリから数センチという大きさで、一般的な甲殻類とは異なり固着生活をしているのですが、雌雄同体であるため生殖が可能です。養殖しているホタテに付着したりするため、邪魔者扱いされていたこともありました。
ふじつぼを一度も食べたことのない人は、どのように食べればよいか分からず、悩んでしまうことが多いです。
しかし、意外と調理の方法は難しくないので、茹でたりして手軽に味わうことができます。
新鮮な状態であれば、刺身にして食べることもあるのです。
嫌な臭みも少なく、柔らかさ・まろやかさを楽しめます。
この機会に、ぜひともご賞味ください。
2016年「ハマグリ」を入荷しました
2016/5/9
ハマグリは、北海道の南部から九州地方まで幅広い地域で生息している二枚貝です。
文様などによって、ミミシロガイ・アブラガイ・アヤハマグリなど、さまざまな名称のものがあるのが特徴です。
珪藻類や有機物などを食べていて、5月から10月にかけての時期が産卵期となっています。
日本国内には2種類がありますが、それ以外は中国・台湾・東南アジアなどからの輸入に頼っています。
バチと呼ばれる外洋性のものは、少しランクが落ちるものとして取り扱われてきましたが、次第に高級品として取り扱われるようになりました。ひな祭りなどのお祝いの場面で多く利用されていて、主に食用となっています。
ハマグリの値段は、主に大きさによって決まっているため、比較的小ぶりな種類のものは安い値段で取引されています。生きているものを選ぶのが原則ですが、その中で美味しいものを選ぶポイントは、表面がぬめっていて光沢があるかどうかです。汁・鍋に入れたり、蒸したり焼いたりする方法で調理されていますが、握りでも多く用いられています。
ハマグリの握りは、江戸前握りの中でも仕事が要求されるネタのひとつで、美味しく作るには本格的な技術が必要になります。まずは、しっかりと洗って、ぬめりを取ることから始めます。そして、酒を入れた鍋を沸騰させて、蓋をして数分間蒸します。貝を開く際は、中身を傷つけないように丁寧にナイフを入れるのがポイントです。
神楽寿司では近海地のモノ、千葉・茨城産のハマグリをお薦めとしてはおつまみで『焼きハマグリ 』 握りで『 炙り 』でご提供致します。
濃厚な貝の香りと旨味が特長で、ほどよくやわらかいけれど味がしっかりあります。
また、はまぐりは体に良くて、お酒との相性も最高です!
是非、この機会にご賞味下さい。
2016年「ボタン海老」を入荷しました
2016/5/2
ボタン海老は、体長が20cmくらいのエビの一種で、橙赤色の体に赤い斑点が見られることが名前の由来となっています。大きな特徴としては、内臓が殻から透けて見えていることが挙げられます。日本海には生息しておらず、北海道の内浦湾から土佐湾辺りにかけての深海に生息しています。
漁獲されるのは10月から5月にかけての時期で、底引き網漁という方法を用いて漁獲します。直径2.7mm前後という小さな卵を産卵しますが、雄性先熟という特殊なタイプなので、途中でオスからメスへと性転換するのです。富山湾で漁獲されているトヤマエビの地方名が「ボタンエビ」なので、混同されることがありますが、別の種類なので注意が必要になります。
ボタン海老は、甘みのある肉質が特徴的で、卵・エビ味噌なども食用になっていますよ。主に刺身や寿司のネタとして食されている魚ですが、あまり漁獲量が多くないため、高級魚として取り扱われています。日本において生で食べられているさまざまなエビの中で、最も高級なものなのです。
魚を食べる際は、どの時期が旬なのかが気になるものですね。ボタン海老の場合は産卵期や抱卵期が長くなっているため旬ははっきりしていませんが、漁獲される主な時期である秋から春にかけてが旬だというのが基本的な考え方になっています。
この機会にぜひともご賞味ください。
2016年「岩手産の牡蠣」を入荷しました
2016/4/25
たいていの人は、牡蠣というと広島県産のものを思い浮かべるものでしょう。
しかし、美味しく食べることができるのは広島県産出のものばかりではないのです。
たとえば、岩手県産のものも独特の味わいがあって、注目を集めるようになっています。
とりわけ美味しいのは、真っ白くて大きな身があります。
岩手県では、牡蠣の食べ放題のお店があったりして、非常に高い人気があります。
実際にお店を訪れてみると、「かきくけこ~」という掛け声を耳にすることがあるのですが、これは「牡蠣を食うから来なさい」といった意味だと考えられています。
養殖が盛んに行われている漁場には、三陸リアス海岸の中心に位置する広田湾の漁場があります。
岩手県産では、赤崎産のものがよく知られているのですが、広田湾産のものは赤崎産のものよりも高値で取引されることが多いんですよ。しっかりとした身がついていて、噛み応え・食べ応えを感じることができるものは、多くの人々の間で愛されてきました。
さまざまな地域で採れるので、1つの地域のものばかりを食べるのではなく、複数の地域のものを食べ比べてみるようにしましょう。美味しいという点はどこでも同じですが、地域ごとに違いが出てくる部分もあるのです。高級感のあるものは高値で取引されていることが多いですが、手頃な価格で食べられるものも少なくありません。濃厚な旨みを持っていて、栄養面でもミネラル分が多い食材です。海のミルクと呼ばれるほど、食べることのメリットも多いです。
できるだけ新鮮な状態で味わう方がよいですよ。
是非、この機会にご賞味下さい。
2016年「真鯛(桜鯛)」を入荷しました
2016/4/18
一般的に、鯛といえば真鯛を指しているといわれます。
日本では重要な魚として位置づけられていて、さまざまな形で食されてきました。
大型のものは全長120cmほどに達するのですが、食用として多く流通しているものは30cmから70cmほどです。
3月から6月頃が産卵期となっていますが、温暖な地域ではより速い時期に産卵期を迎えます。
ちょうど春の訪れと共に開花する桜の花びらを模した可愛らしい斑点模様があしらわれた美しい真鯛のことを桜鯛と呼びます。また、この斑点模様はオスの真鯛にのみ現れる特徴です。
北海道以南から尖閣諸島の辺りに分布していて、岩礁・砂礫・砂底などを好んで生息しています。
日本においては古くから「めでたい」という表現とかけて用いられていて、お祝いの場面などで食卓に並べられることが多かったです。
地域によって異なる呼び名がついていることも、真鯛の特徴の1つとなっています。
たとえば、関西地方ではチャリコ、島根県ではホンダチ、高知県ではタイゴというように、初めて見ると何の魚なのか分からないことも多いといわれています。
さまざまな食べ方があることでも知られていて、刺身・塩焼き・煮つけなど、どのような食べ方をしても美味しさを堪能することができます。少しでも美味しいものを選ぶためには、表面の色が鮮やかな赤になっているかどうか、斑紋がコバルトブルーではっきりしているかどうか、といった点に注意してみましょう。この時期に漁獲される真鯛は脂が乗っていて美味しいと評判です。あまり市場に出回ることがないため、高値で取り引きされています。
真鯛は、豊富なたんぱく質を含んでいる反面、あまり脂質はないのが特徴です。疲労回復などに役立つクレアチンを多く含むため、運動をする機会がある人に向いています。
この機会にぜひともご賞味ください。