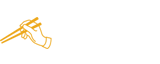築地新館
築地でお気軽江戸前寿司
2015年「真鱈の白子」入荷しました!
2015/10/29
今年も真鱈の白子が入荷しました。白子とは魚の精巣のことで、真鱈の白子は真子とも呼ばれ、
同じ仲間のスケソウダラの白子(助子)と区別されます。
スケソウダラの白子と比べると形が大きく、味も良いため高値で取引されます。
つきぢ神楽で提供している白子は新鮮な国産もので、
その名の通り雪のように白く、くせの無いクリーミーな味わいが身上です。
さっぱりとしたポン酢の酸味が絶妙なバランス。白子の濃厚な甘味を一層引き立ててくれます。
口いっぱいに広がる深い味わいは一度食べたら病みつきで、お酒がさらに美味しくいただけること請け合いです。
ただし、飲みすぎには十分ご注意を!
真鱈はサケと並び北国の魚の代表格で、1m以上の大きさになることもあります。
非常に大食漢で、お腹が膨らんでいることから、「たらふく食べる」の語源とも言われております。
実際におなかを調べてみると、少なくない数の真鱈の胃袋には潰瘍があり、
食べ過ぎによるものと見られているそうです。
鱈という漢字は「魚へんに雪」と書きますが、雪の降る冬の時期によく獲れるためこの字があてられたということです。
その身も真っ白な白身で、まさに寒くなるこれからの季節が旬です。
2015年「あん肝」入荷しました!!
2015/10/23
アンコウの見た目はとてもグロテスク。つぶれたような体に巨大な頭。口には鋭い歯がびっしり・・・。しかし、その身はは淡白で脂肪が少なくコラーゲンが豊富。低カロリーなため、女性にも人気です。
アンコウは七つ道具と呼ばれる「肉・肝・水袋(胃)・ぬの(卵巣)・えら・ひれ・皮」のほかにも「尾ひれ・あご・ほお肉(柳肉)」など骨以外捨てるところがない魚です。中でもキモはやっぱり「あん肝」。アンコウの価値はあん肝の大きさで決まると言われているほどです。その旬は産卵前の時期である秋口~春先です。
最近は輸入物が多く出回っており、時期によっては冷凍もの・缶詰しか手に入らなかったりしますが、ここ築地で提供するのはもちろん国産の新鮮なもの。生臭さはなく、ねっとりとした食感と濃厚な旨みは一度たべたらやみつきになります。これからの季節、あん肝を肴に一杯。こたえられません!
あん肝はフォアグラと並ぶ珍味とされ、栄養価的にも非常に優れています。アンコウは餌の少ない深海に棲むため、餌の栄養を肝臓に脂肪として蓄え少しずつ使うためといいます。
ビタミンA、ビタミンB12、ビタミンD、ビタミンE、セレンが豊富に含まれ、いずれの栄養素も全食品類の中でトップクラスです。眼精疲労の改善、免疫力向上、滋養強壮、貧血予防、老化防止、骨粗鬆症の予防、抗血栓作用などの効果が期待できます。また、今話題のオレイン酸やエイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)も多いので動脈硬化の予防も見込めます。
食べておいしく、健康にも良いあん肝。是非お試しください!
2015年 「のどぐろ」を入荷しました!
2015/10/5
「のどぐろ」という名前、実は俗称で標準和名は「あかむつ」と言います。
ちなみに「のどぐろ」という名前は、口を開けて中をのぞくと喉の奥が黒色をしていることが由来です。
背が赤く、腹側も赤身を帯び40センチ前後で形は平凡で特徴がありません。
昨年、9月17日(水)日本テレビ「ZIP!」にて
当店【つきぢ神楽寿司 新館】が取り上げられました。
テニスの錦織圭選手が記者会見の中で語った「のどぐろとか食べたいです」の一言で、
急遽、当店まで「のどぐろ」についての取材がございました。
つきぢ神楽寿司は錦織選手を応援しております!
「のどぐろ」は市場でも超がつくほど高級魚として扱われている魚で、東北、北陸以南の日本海、
太平洋に広く分布しており特に山陰沖から対馬近海にかけて漁獲されていますが漁獲量はそれほど多くはありません。
季節を問わず脂の乗りが良く、いつ食べても旨いと食通に絶賛されています。
旬は、秋から冬にかけてになります。白身で脂が身に混ざり込んでいてクセのない味わいです。
脂がのり濃厚な旨みを感じさせてくれることから「白身のトロ」と呼ばれています。
秋から冬にかけて旬ですので、是非ご賞味下さい!
2015年 「鮭児(ケイジ)」を入荷予定!
2015/9/28
鮭児とは、10月から11月にかけて世界自然遺産・知床周辺などで漁獲されるあぶらののった若いサケのことです。
通常のサケと見分ける箇所は、腹を開けて胃袋の下側についている幽門垂の数を調べることで、
その数が220個程度あれば「鮭児」である場合が多く、卵巣、精巣が未成熟です。
漁獲量は、普通のサケ1万匹に対して1~2匹の割合でしか獲れないため「幻の魚」として重宝されています。
その姿かたちは、こぶりでありながら一際目を引き、青々とした背中に脂のりのよさを思わせる銀色の魚体。
体長のわりに、ずんぐりとした丸みのある胴体で頭が小さく見た目も綺麗で、
漁師ならずとも「普通の鮭とは少々違う」とわかるはずです。
秋鮭と同じシロサケに分類されますが、
鮭児は他の鮭と違い産卵のために海に戻ってくるのではなく搾餌回遊中に水揚げされるので、
お腹に卵や白子が入っていないため、その分魚体に脂がまわっています。
その身は大変脂が乗っており、
脂肪率が通常のサケの2~15%に対して鮭児は20~30%あり、まさに全身トロ状態と言われています。
近年では、相場も高騰して羅臼市場のセリ値は1尾10万円超えともされています。
このため高級食材として珍重されています。
魚体は青みかかった流線型で小ぶりでずんぐりして、尾びれがピンク色しているなどの特徴があり、
脂肪の比率が通常のサケより極めて高く、刺身で食べると舌の上でとろける味は絶品です。
鮭児ならではのあの強い脂がのりつつも、
とろっと軽い口当たりで、くどさや臭みがなく絶妙な風味があり、まさに美味淡麗な逸品です。
一生に一度は食べてみたい、幻の鮭を是非ご賞味下さい!
2015年 「鯖(さば)」を入荷しました!
2015/9/21
日本の太平洋各地で水揚げされるサバは秋が旬で「秋サバ」と称されます。
太平洋沿岸を回遊するサバは、伊豆半島沖で春頃産卵し餌を食べながら北上します。
北海道沖での海域は、プランクトンが豊富にありサバは丸々と太りますが、
脂肪分は皮と身の間などに貯められ身に均等にまわりません。
このサバが産卵のために南下を始める時期が9月から10月頃であり、
この時期のサバは脂肪が身に入りこみ身もしまり風味は格段に上がります。
ここで少し雑学ですが、得しようとして数をごまかすことを 『さばを読む』 と言いますね。
この「さば」は魚の鯖のことでしょうか?
実は、これには二つの説があります。
一つは鯖説です。
鯖はとても傷みやすい魚なので、市場へ搬入されるとすばやく仕分けしなければなりません。
一応数は数えてあるのですが、そのスピードがあまりにも早すぎて、
あとで数を合わせても合ったためしがないくらいだったそうです。
このことから、数をごまかすのを 『さばを読む』 というようになったという説。
もう一つは、さばは米粒を指すそうです。
昔、お寿司屋さんは、お客さんが食べた寿司の数を覚えておくために、
まな板の隅に米粒を並べていました最後にその米粒の数を数えてお勘定をするのですが、
たまにお客さんから 『そんなに食べていない』 と文句を言われることがあり、
そのときの板前さんの反論が『さばを読んでいるので間違いない』だったそうです。
しかし、お客さんにとっては、 『さばを読む』=『高い請求』 としか取れず
現在はその意味で使われるようになったと言う説です。
そんなサバですが、脂が程良くのっていながら身が締まり刺身が絶品です。
また、脳の発達に大切な役割を果たすDHAの宝庫で、
コレステロールや中性脂肪を下げる作用があるEPAが豊富です。
健康・美容に欠かせないビタミンA、B1、B2など
現代人が不足しがちなミネラルやカルシウムがたっぷり詰まった健康食として注目されています。
旬のこの時期、是非ご賞味下さい!